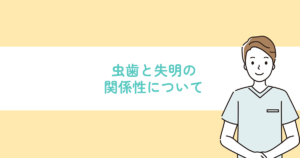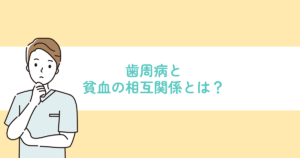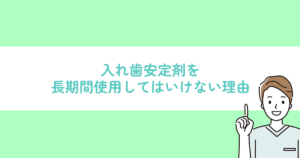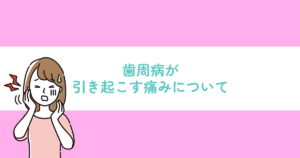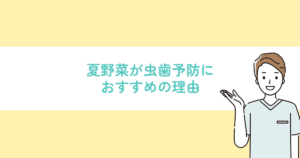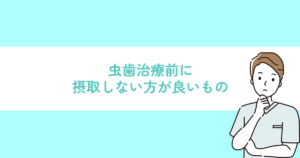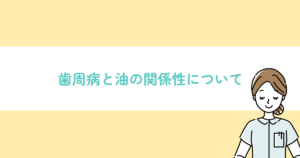歯槽膿漏は重度にまで進行した歯周病であり、ここまで達した場合は簡単に治療することができません。
また歯槽膿漏が引き起こす合併症も多く、そのうちの一つに鼻の疾患である副鼻腔炎が挙げられます。
今回は、歯槽膿漏によって発症する副鼻腔炎の概要、発症の仕組みなどについて解説します。
副鼻腔炎の概要
副鼻腔炎は、鼻の中の鼻腔の周りにある副鼻腔が炎症を起こす疾患です。
発症すると鼻水や鼻づまりなどが起こりやすくなり、場合によっては頬や両目の間の痛み、額などの頭痛が見られることもあります。
また副鼻腔炎は急性副鼻腔炎、慢性副鼻腔炎の大きく2つに分けられますが、歯槽膿漏が原因の場合は歯性副鼻腔炎という特殊なものに該当します。
ちなみに副鼻腔炎は、重度の歯周病である歯槽膿漏だけでなく、虫歯が原因で発症することもあります。
歯槽膿漏が副鼻腔炎を引き起こす仕組み
歯槽膿漏は歯周病が悪化した状態であるため、そのまま放置していても治ることがありません。
むしろ歯科クリニックで治療を受けない限り、どんどん悪化していきます。
また歯槽膿漏が悪化すると、歯周病菌が血管を通して全身に回り、副鼻腔に細菌が繁殖して膿が溜まります。
このとき形成された膿を歯根嚢胞といいますが、最終的に歯根嚢胞の中の細菌が副鼻腔に入ると、副鼻腔炎を発症します。
ちなみに副鼻腔炎を発症すると奥歯の根元、歯の神経に波及し、虫歯ではないにもかかわらず痛みが出ることも考えられます。
副鼻腔炎を発症した場合の対処法
通常、副鼻腔炎を発症した場合は耳鼻科のクリニックを訪れて治療します。
しかし歯性副鼻腔炎は耳鼻科では治療できません。
痛み止めや抗生物質で一時的に抑えることは可能ですが、こちらはあくまで対症療法です。
そのため、歯槽膿漏の症状と副鼻腔炎の症状がどちらもある場合は、歯科クリニックを訪れましょう。
歯性副鼻腔炎の診断は、患者さんからの問診とレントゲン、CT撮影で行います。
副鼻腔は空洞であるため、レントゲンやCTで撮影した場合、通常は真っ黒に写ります。
一方、副鼻腔炎を発症している方は真っ白に写るため、そのような場合はまず抜歯を含む歯槽膿漏の治療を受けなければいけません。
まとめ
歯槽膿漏は治療が困難な歯周病であり、発症している時点で口内環境は深刻な状態です。
しかしそれでも治療を受けずにいると、今度は全身にまで影響を与えるようになります。
また副鼻腔炎を発症してしまうと、場合によっては歯槽膿漏の治療でも改善せず、歯科クリニック以外の医療機関で大規模な外科治療を受けなければいけないこともあります。