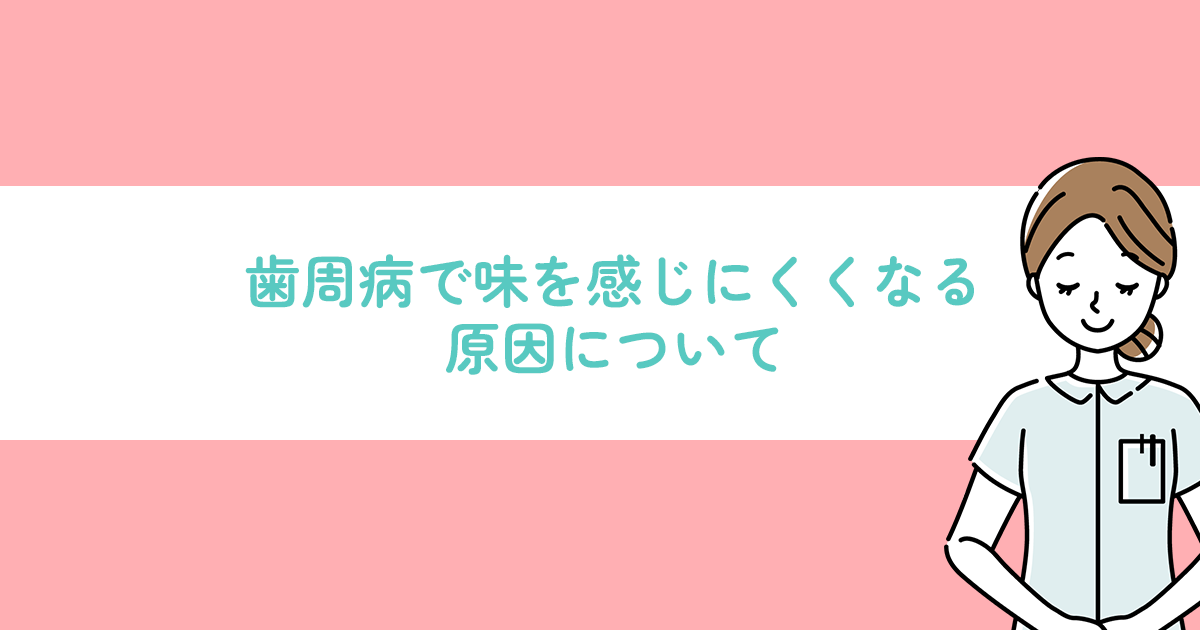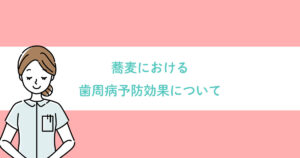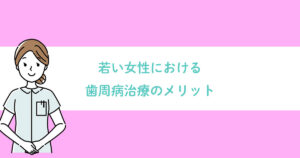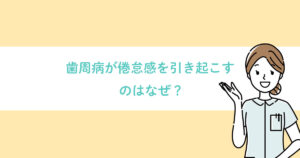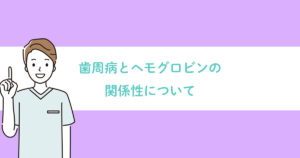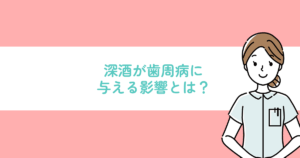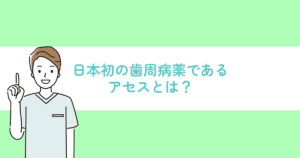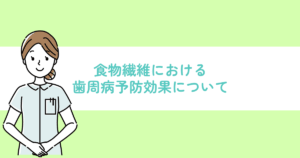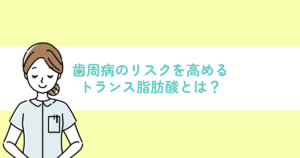歯周病の主な症状としては、歯茎の腫れや出血などが挙げられますが、実際は他にもさまざまな症状が現れます。
またその症状の一つに、食事の味を感じにくくなるということが挙げられます。
今回は、歯周病が味覚を鈍らせてしまう原因や、味を感じにくくなることのデメリットなどについて解説します。
歯周病で味を感じにくくなる原因
歯周病を発症すると、口内の細菌が繁殖しやすくなります。
これにより、舌の表面に細菌の塊である舌苔が厚く堆積することが考えられます。
舌苔は、味を感じる器官である味蕾を物理的に覆ってしまうため、量が多ければ多いほど味を感じにくくなります。
また口内の細菌が活動することにより、苦味や金属味といった不快な味のものが産生され、味覚が阻害されることもあります。
こちらは人によっては、“食べ物の味が変になった”と感じることもあります。
さらに、歯周病の方は磨き残しが多いケースもよく見られるため、常に味覚が変化してしまう可能性は高いです。
味を感じにくくなることのデメリット
味を感じにくくなることで、栄養不足や体力の低下、生活習慣病のリスク増加などにつながります。
味があまり感じられないと、食事への満足感が得られずに食欲が低下します。
結果的に、食事量が減少して栄養不足や体力・抵抗力の低下を招きます。
また味を感じにくい場合、味付けをいつもよりも濃くしてしまう傾向にあります。
特に塩味や甘味を感じにくい場合、塩分や糖分を過剰摂取しやすくなり、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を誘発してしまうおそれがあります。
歯周病で味を感じにくい場合の対策
歯周病で味を感じにくくなってしまった場合は、まず歯科クリニックを受診し、口腔内全体の状態を診てもらうことが大切です。
また歯周病が原因であれば、専門的な治療と日々のセルフケアによって口腔衛生状態を改善することで、味覚も回復する可能性があります。
ここでいうセルフケアには、歯のブラッシングだけでなく舌磨きも含まれています。
さらに味覚障害は栄養不足やストレス、薬の副作用や全身疾患などの原因でも起こるため、歯科クリニックで特定できない場合は他の診療科の受診も検討してください。
まとめ
歯周病には、皆さんがよく知っている症状以外にもさまざまな症状があります。
しかし、歯茎の腫れなどわかりやすい症状でなければ、それが歯周病によるものとすぐに気づくのは難しいです。
これには当然味覚障害も含まれるため、歯周病の早期発見するためには、やはり日頃から歯科クリニックに通う習慣をつけておかなければいけません。